自筆証書遺言の検認、今までとこれから
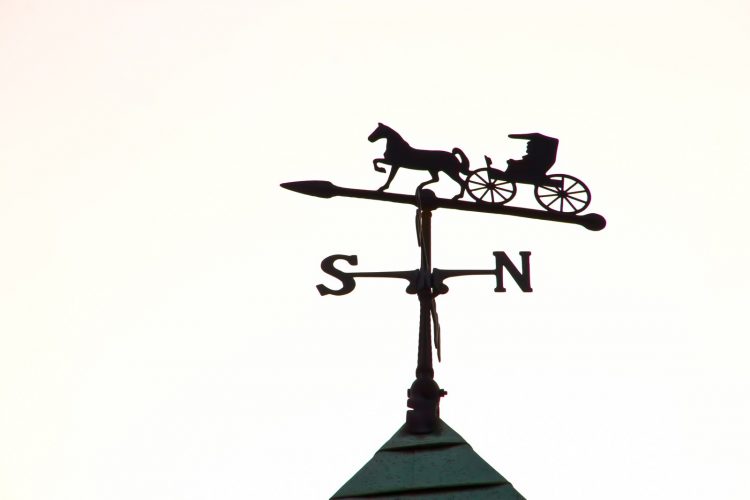
今回の民法(相続法)改正により、曖昧なものが明確になったり、厳格なものが緩和されたりと様々な変更が行なわれましたが、それに伴い新たな制度が創設もされました。
その一つが「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法・2020年7月10日施行)」の制定による「自筆証書遺言の保管制度の創設」です。
これにより何が一番変わるのかというと、この制度を利用した場合には家庭裁判所における自筆証書遺言の「検認」が不要になるということです。自筆証書遺言利用の最大の障壁となっていたと言っても良い「検認」が不要となることで、遺言作成を促進しようという狙いもあるようです。(自筆証書遺言方式緩和も遺言作成を促進する狙いがあるようです。)
自筆証書遺言は公正証書遺言に比べ、遺言者が1人で作成できるという意味においては手軽に作成できる遺言ですが、法的要件を満たす必要があること、相続開始後には家庭裁判所の「検認」を受けなかればならないこと、偽造・変造、破棄、紛失などのリスクがあることなど、手軽に作成できそうでいて法的障壁や心ない者によるリスク等などもありました。
今回の新制度を利用すれば前述したような法的障壁のみならず偽造・変造、破棄、紛失等のリスクも回避できるというメリットがあります。
では、今後新制度によって自筆証書遺言がどうなるのか、特に「検認」はどうなるのか、簡単にみていきたいと思います。
自筆証書遺言を作成した場合に、遺言をもとに遺言執行をするときは、家庭裁判所の発行する「検認済証」が必要になります。金融機関等の手続きの際には自筆証書遺言の写しとともに「検認済証」の提出が求められます。
「検認」は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出して行ないます。その際に、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人の属性に応じた戸籍謄本を添付しなければならず、一般の方が行なうには手間のかかる作業となります。その後、家庭裁判所から「検認期日」の通知が来ますので、相続人は原則として出席しなければなりません。
このように、遺言者にとっては比較的楽な自筆証書遺言ですが、相続人にとってはかなり手間のかかる遺言になってしまうわけです。
公正証書遺言には手が出しづらい、しかし自筆証書遺言では「検認」の手間などを考えると作成を躊躇してしまう、などの理由で遺言作成を先送りにしていた方などは今回の法改正により自筆証書遺言が制度的に利用し易くなったのかもしれません。
「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法・2020年7月10日施行)」は遺言者自身が遺言書保管所である法務局に遺言書の保管申請を行ない、法務局の遺言書保管官が申請された遺言が民法968条の規定を満たしているかなど外形的審査を行うので、自筆証書遺言の法的要件を満たさないというリスクは解消されます。そして、遺言者の本人確認により、当該遺言が申請者本人のよって作成されたものであることを確認します。また、法務局が保管することで隠匿・変造、紛失リスク等も解消されます。
このようなことから、検認手続きで行なわれてきた遺言書の状態の確定や現状を明確にする必要性が低いということで、「自筆証書遺言の保管制度」を利用した場合には「検認」は不要ということになります。
では、「自筆証書遺言の保管制度」を利用しない場合にはどうか、残念ながら今まで通りの家庭裁判所の「検認」が必要となります。
2020年7月10日以降の自筆証書遺言の作成は、「自筆証書遺言の保管制度」を利用するか否かで「検認」の「要・不要」が分かれます。
今回の改正を受けて、金融機関等の対応もどうなるのか、「自筆証書遺言の保管制度」のスタートまであと約1年です、この1年で各機関も詳細を詰めていくのではないでしょうか。
制度の詳細だけではなく、各機関の対応等も確認して、自筆証書遺言なのか、公正証書遺言なのか慎重に決めていかなければならないと思います。
このページのコンテンツを書いた相続士
- 行政書士、宅地建物取引士、相続士上級、CFP
東京都小平市出身。法政大学経済学部卒。リース業界・損害保険業界を経て、2007年相続に特化した事務所を開設し、現在も一貫して「円満相続と安心終活」をモットーに相続・終活の総合支援を行っている。相続・終活における問題の所在と解決の方向性を示す的確なマネジメントと親身な対応が好評を得ている。相続専門家講座の専任講師として相続専門家の育成にも助力している。日本相続士協会専務理事。
中島行政書士相続法務事務所・ナカジマ相続士事務所
この相続士の最近の記事
 スキルアップ情報2024.11.15相続士業務の広がり
スキルアップ情報2024.11.15相続士業務の広がり スキルアップ情報2024.10.14終活・・・横須賀市の取組から
スキルアップ情報2024.10.14終活・・・横須賀市の取組から スキルアップ情報2024.09.04戸籍の振り仮名制度
スキルアップ情報2024.09.04戸籍の振り仮名制度 スキルアップ情報2024.08.09「終活無意味論」に関する考察
スキルアップ情報2024.08.09「終活無意味論」に関する考察
相続士資格試験・資格認定講習のお知らせ

