死因贈与とは何か

自身の死後に、どの財産を誰に相続させるかを決める方法として「遺言」の作成がありますが、「死因贈与」という方法で財産を渡すこともできます。今回は死因贈与とは何か、その内容と活用する際の注意点等についてお伝えします。
■死因贈与とは
死因贈与とは、死亡を原因として贈与を行う行為となります。例えば、「贈与者(財産を渡す人)甲の死亡を条件として受贈者(財産を受け取る人)乙に不動産丙を贈与する」旨を約束することがあてはまります。受贈者が取得した財産は贈与税の課税対象ではなく相続税の課税対象となります。
遺言と似た行為ですが、遺言は自身の財産をどのように・誰に渡すかを決める、遺言者の意思表示・単独行為であるのに対して、死因贈与は、贈与者・受贈者双方の明確な意思・合意によって行われる契約行為であるということが大きな違いです。
また遺言は自筆証書遺言・公正証書遺言等、書面で行うことが必要となりますが、死因贈与は通常の贈与と同じく書面で契約書を交わしても構いませんし、口頭で約束をしても契約が成立する点が違いとなります。
ただし契約書を交わさない場合、その内容が贈与者・受贈者当人以外は知ることができないため、通常は契約書を交わしその内容を書面で残しておくことが一般的です。
さらに遺言はその内容を、財産を渡す側に必ずしも知らせる必要はありませんが、死因贈与の場合には契約であるため、贈与する財産が明確になっている、生前に受贈者に渡す財産を伝えることができる点も違いとなります。
■死因贈与の種類
このように遺言とは違う特徴を持つ死因贈与ですが、単純に贈与者の死亡を条件として受贈者に財産を贈与する契約の他、次のような贈与も行うことができます。
・負担付死因贈与
こちらは死因贈与をする条件として、生前に受贈者に何らかの負担・義務等を負わせる契約をするものです。例えば、死後に不動産を贈与する代わりに、生前に贈与者の介護等身の回りの世話を行う、という内容があてはまります。ちなみに死因贈与については「その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する」とされています。
民法
(死因贈与)
第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
ですので、死因贈与の撤回についても遺贈に関する規定に基づき、いつでも撤回することが可能となります。
(遺言の撤回)
第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
ただし負担付贈与の場合には、その負担を受贈者が全部またはこれに類する程度履行した場合には、「特段の事情」が無い限り撤回することができないという判例があります。これは受贈者にとっては、負担・義務等を負わされた後に契約を撤回されるというリスクを軽減できる他、その負担・義務等を履行することにより財産を取得できる権利が得られるというメリットもあります。
・始期付所有権移転仮登記
死因贈与によって渡す財産が不動産の場合、贈与者の承諾があれば「始期付所有権移転仮登記」を受贈者が単独で申請することができます。こちらは死因贈与契約書を公正証書にて作成し、その中に贈与者が仮登記の申請について承諾することと、死因贈与契約の執行者を受贈者と指定することを記載しておけば、受贈者が該当の不動産について単独で所有権移転登記の手続きを行うことができ、確実に財産を取得することが可能となります。
■活用する場合の注意点
このように死因贈与には遺言とは違う特徴があり、活用の仕方によってはメリットがありますが、受遺者が法定相続人で、死因贈与によって不動産を取得した場合には、遺言と比較して登録免許税・不動産取得税の税率が変わってきます。
登録免許税は遺言の場合には0.4%に対して死因贈与は2%、不動産取得税は遺言の場合には非課税に対して死因贈与は4%と、負担額が大きくなります。
また、先にもお伝えしたとおり、贈与契約は必ずしも書面で行う必要が無いものの、後々トラブル等を起こさないためにも書面で契約内容を残しておいたほうが望ましいと言えます。
生前に自身の財産の処分方法について決められる死因贈与ですが、遺言等他の方法と合わせてできるだけ自身の意思が反映できる方法を選択することが必要となります。
このページのコンテンツを書いた相続士
- 相続士、AFP
1971年東京都生まれ。FP事務所FP EYE代表。NPO法人日本相続士協会理事・相続士・AFP。設計事務所勤務を経て、2005年にFPとして独立。これまでコンサルティングを通じて約1,000世帯の家庭と関わる。
相続税評価額算出のための土地評価・現況調査・測量や、遺産分割対策、生命保険の活用等、専門家とチームを組みクライアントへ相続対策のアドバイスを行っている。設計事務所勤務の経験を活かし土地評価のための図面作成も手掛ける。
また、住宅購入時の物件選びやローン計画・保険の見直し・資産形成等、各家庭に合ったライフプランの作成や資金計画のサポートを行っている。個人・法人顧客のコンサルティングを行うほか、セミナー講師・執筆等も行う実務家FPとして活動中。
FP EYE 澤田朗FP事務所
この相続士の最近の記事
 スキルアップ情報2025.04.25死因贈与とは何か
スキルアップ情報2025.04.25死因贈与とは何か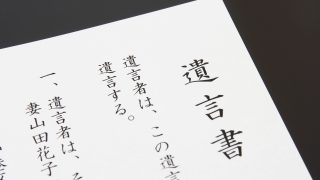 スキルアップ情報2025.04.21財産を「遺贈する」旨の遺言
スキルアップ情報2025.04.21財産を「遺贈する」旨の遺言 スキルアップ情報2025.04.14がけ地がある土地の相続税評価額の計算方法
スキルアップ情報2025.04.14がけ地がある土地の相続税評価額の計算方法 相続不動産2025.04.07上空に高圧線が通っている土地の相続税評価額
相続不動産2025.04.07上空に高圧線が通っている土地の相続税評価額
相続士資格試験・資格認定講習のお知らせ

